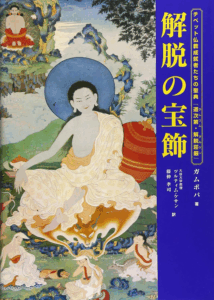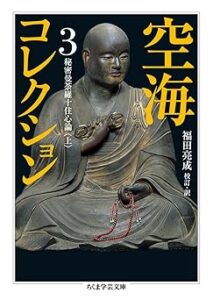習い事や宗教的な修行において重要なのは、「意識が意識的であること」です。たとえば瞑想中に「光が見えた」「仏が見えた」「観音様からお告げを受けた」といった神秘体験をすることがありますが、これらの多くは、意識が受動的になり、無意識から自然に湧き上がってきたイメージ――つまり「空想」である場合がほとんどです。
習い事においても、「守破離」という教えがあるように、まずは「師匠の言うとおりにする」「師匠の真似をする」といった段階から始めます。このときの重要なのは、やはり「意識的であること」です。
「空想」と「観想」は、いずれも心の中で何かを思い描くという点では共通していますが、その性質と方向性には明確な違いがあります。
空想(くうそう)
特徴
- 無意識から湧き上がるイメージに、意識を受動的に委ねること。意識の主導性が弱いため、イメージがあちらこちらに流されやすい。
- 現実には存在しないこと、実現しそうにないことを自由に想像すること。現実の制約を超えた発想が可能なため、芸術や創造の源泉となる。
例
- 白馬に乗った王子様が迎えに来る
- 空を自由に飛び回る
- 誰もが平和に暮らす理想郷を思い描く
- 習い事において、自分のクセや間違いに気づかず、「うまくできているつもり」になる状態
観想(かんそう)
特徴
- 無意識に生じるイメージや感情を排除し、意識的に特定の対象の像や感情を形成すること。
- 意識を現実的な対象や内面、あるいは抽象的な概念に集中させること。
- 静かに心を落ち着け、一つの対象に意識を向け続けるという点で、瞑想や修行と共通する。
例
- 習い事のイメージトレーニング
- 呼吸法において、呼吸筋や吸気・呼気の流れに意識を向ける
- 仏教の「慈悲の瞑想」(慈:衆生を慈しみ、楽を与える/悲:衆生を憐れみ、苦を除く)
- 仏を具体的なイメージとして心に描き、観想する

空想と観想の本質的な違い
両者の違いは、「意識的にイメージを作っているかどうか」にあります。
英語でも、「空想する」は imagine、「観想する」は visualize と区別されます。このニュアンスの違いは明確で、観想は流れに任せてただ想像する imagine ではなく、意識的・具体的にイメージを描き出す visualize なのです。
カルマの視点かみた空想と観想
カルマの観点から考えると、無意識に浮かぶイメージや感情に意識を委ねるのは、「カルマの流れに乗ったイメージング」と言えます。一方で、意識的にイメージや感情を形成することは、カルマに棹さして流れに逆らう行為です。
世俗的な行いであっても、何かを新たに身につけること、善業を積むこと、瞑想修行を行うことは、すべて徹底的に「意識的な行為」である必要があります。最終的には「意識的・無意識的」という区別すら超えた意識状態を目指すわけですが、そのためにもまずは「徹底的に意識的であること」が何より大切なのです。