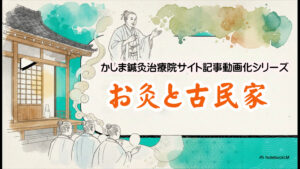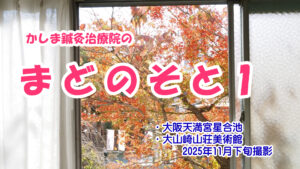伝統医学を学ぶ際の基本前提はいろいろありますが、今回は立ち位置の話をします。
たとえば仏教で密教を学ぶときに加行を受けずとも、密教経典や儀軌を毎日何時間も勉強すれば密教の核心が分かる、なんて考える阿闍梨は皆無でしょう。⚪︎⚪︎流のお花やお茶、あるいは能や狂言を学ぶときに、本やビデオを見るだけでそれが身につくと考える人もいないと思われます。ところが中国の古医書を学ぶ人には書物を読み込んで独自解釈したものを伝統と呼ぶ人が一定数存在します。
伝統文化を学ぶということはそれを受け継ぐ先達から学ぶから伝統なのであって、たくさんの書物を読み込んで独自解釈の体系を作り上げても、それを伝統とは呼びません。伝統とは従来の体系をさらに推し進めて独自解釈を付加することはあっても(伝統の深化ですね)、伝統を無視して独自解釈の体系を構築することではありません。これらはなんらかの伝統文化を学んだことがある人ならどういう意味かすぐ分かるはずです。
そもそもどの分野であっても古典の中には「正しく伝えるために書かれたものではない古典」が一定数存在します。たとえば仏教の密教文献や道教文献の理解にあたっては他の書物に「学術的根拠」を求めても無意味なことが多々あります。なぜならそれを書いた流儀の門内の口伝がないと読み解けないように記述されているからです。大学の学部レベルでも専門的学んだ人なら常識でしょう。『黄帝内経』もそういう系統の書物です。『鍼灸大成』や『景岳全書』とは記述スタイルが違うのです。個人で記述されたものと、何人もの手によって編纂されたという違いもありますが。
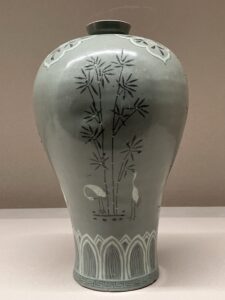
そういう伝統文化を学ぶ際の基本的な視点が欠落しているのに、「お前はどれだけ古典を読んだのか」とマウントを取り、自分の立ち位置を振り替えないのではつける薬がないです。そんなことするくらいなら伝統と呼ばずにオレ様流で構築して実績あげる方がいいと思います。
神田神保町の仙人氏が言った「日本に伝統鍼灸なんてない」という指摘は示唆に富む発言ではあります。まあ経絡治療あたりだと伝統100年弱といってもいいかもしれませんけどね。
とはいうものの、それを踏まえて江戸期の⚪︎⚪︎流鍼灸術の復興というこで文献資料をもとに再構築する試みを、伝統に沿ったものかどうかを懐疑的になりながら探る試みは尊敬に値します。